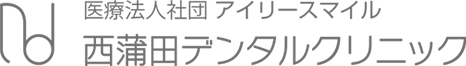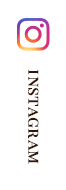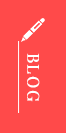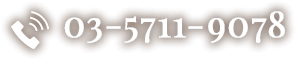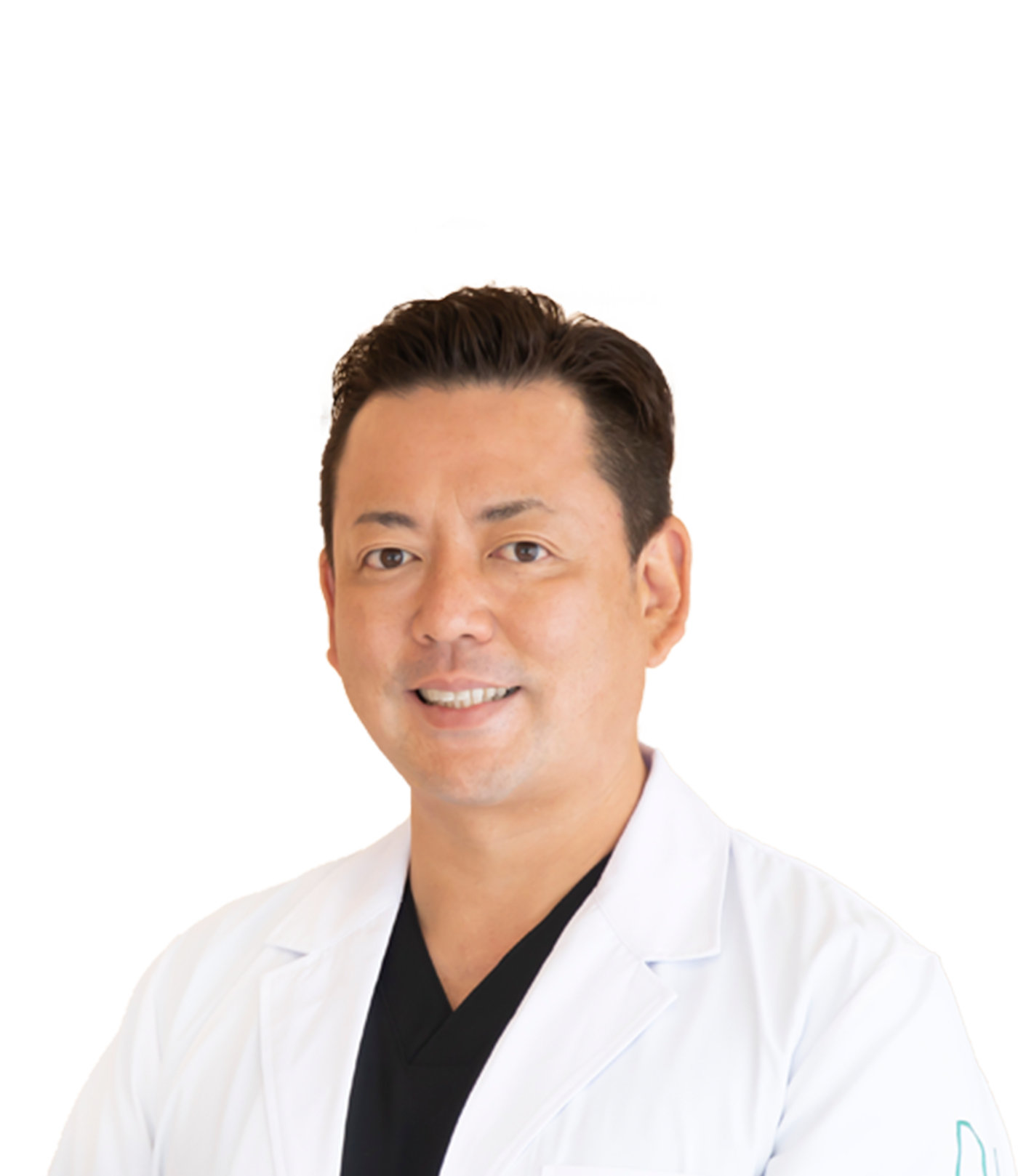鏡を見たとき、写真を撮ったとき、「歯の色がおかしい」と感じることはありませんか?実は、歯の変色は見た目の問題だけでなく、健康状態を示すサインとして現れている可能性もあります。
そこでこの記事では、歯の変色が起こる原因と、改善するための方法について詳しく解説します。自らの歯の変色タイプを知り、適切な対策を取って健康で美しい歯を取り戻しましょう。
歯の変色とは

歯の変色とは、何かしらの原因によって表面や周辺の色が変わってしまう状態のことです。鏡で自らの口元を見たときに「ここだけ色が違う」「この黄ばみは何だろう?」と感じて気づくケースがほとんどです。
実際、厚生労働省が公開した調査では、歯の色は、歯科口腔の問題のなかでもっとも高い割合(全体の20.4%)で悩みとして挙げられています。なかでも女性は男性よりも歯の色に悩む傾向があり、40代女性では約31.7%が歯の色に悩んでいるという結果も出ています。
なかでも、歯の変色は見た目の問題だけでなく、健康上の問題を示すサインの可能性もあるので注意が必要です。早期に原因を特定し、適切な対処を行いましょう。
参考:厚生労働省:歯科口腔保健支援事業(歯科口腔保健の実態等に関する調査)
歯の変色の種類
歯の変色の種類は、大きく「外因性」と「内因性」の2つに分類できます。
外因性は外部からの影響で、歯の表面に限って発生する変色です。例えば、コーヒーやタバコなどによる着色がこれに当たります。
一方、内因性は体の内部からの影響による変色で、生まれつきのものから後天的なものまでさまざまです。加齢による自然な黄ばみや、薬の影響などがこれに含まれます。
いずれにおいても、原因によって対処法も異なるため、自らの歯の変色がどの原因によるものかを見極めることが肝要です。次では、外因性と内因性にわけて、発生しやすい原因を見ていきましょう。
【外因性】歯の変色が起こる5つの原因

外因性の歯の変色は、外部からの要因で歯の表面に色素が付着することで起こります。主な原因としては以下が挙げられます。
- 食べ物や飲み物による着色
- タバコのヤニによる変色
- 歯垢や歯石の蓄積
- 虫歯による黒ずみや茶色への変色
- 洗口液の長期使用
食べ物や飲み物による着色
色素の濃い食べ物や飲み物を摂取すると、その色素が歯に付着して変色の原因になります。歯の表面にあるエナメル質は薄く透明な保護膜で覆われていますが、この膜が飲食物の汚れを付着させてしまうからです。
着色しやすい飲食物としては、以下のとおりです。
- コーヒー(タンニン)
- 紅茶(タンニン)
- 赤ワイン(ポリフェノール)
- カレー(ターメリック)
- 烏龍茶(カテキン)
- チョコレート(ポリフェノール)
この飲食物を頻繁に摂取する人ほど、歯の着色が進みやすくなります。通常、飲食後すぐに歯を磨くか、水でうがいをすることで着色を軽減できます。
着色は表面的なものなので、歯科医院でのクリーニングで除去可能です。日常的なケアを心がけるだけでも、美しい歯の色を維持できます。
タバコのヤニによる変色
タバコや葉巻に含まれるヤニ(タール)が歯に付着して、歯全体が均一に黄色や茶色に変色します。ヤニには強い粘着力があり、ほかの飲食物の色素もくっつける性質があります。そのため、喫煙者の歯が黄ばみやすいからです。
主に、歯と歯の間や歯と歯茎の境目に着色しやすい傾向があり、長期間の喫煙で変色が濃くなったり、受動喫煙でも影響を受けたりするケースもあります。また、喫煙量や期間によって変色の程度も異なります。
加えて、電子タバコでも程度は低いものの着色の原因になることも分かっています。禁煙できれば新たな着色を防ぐことができますが、すでについた着色は歯科医院でのクリーニングやホワイトニングで対処する必要があります。
歯垢や歯石の蓄積
歯垢(プラーク)とは、口内の細菌が繁殖して白く固まったもののことです。この歯垢を放置すると唾液中のカルシウムなどと結びついて「歯石(細菌の死骸の塊)」になり、歯ブラシでは完全に除去できません。
こうして生まれた歯石は白色や乳白色ですが、徐々に黄色や黒色に変わっていきます。歯と歯茎の境目で特に蓄積しやすく、ざらざらした感触があるのが特徴です。
また、歯垢のなかには色素を作り出す細菌もあり、オレンジや緑色に変色することもあります。蓄積した歯垢や歯石は歯周病の原因にもなるため、定期的な歯科クリーニングを受けることが重要です。
虫歯による黒ずみや茶色への変色
虫歯は、ミュータンス菌などの細菌が作り出した酸によって歯が溶ける病気です。進行すると空洞ができてしまうだけでなく、歯の色も変化して黒ずみや茶色への変色が現れます。
虫歯による変色の進行過程は、以下のとおりです。
- 初期:白く濁る(エナメル質の脱灰)
- 中期:薄茶色に変色
- 後期:茶褐色から黒色に変色
- 末期:歯が欠けたり、穴が開いたりする
初期虫歯は無症状で、変色もわかりにくいです。そのまま象牙質まで虫歯が進行すると、歯が溶けて変色も目立つようになります。放置すればするほど治療の費用も期間も増加してしまいますので、痛みがなくても早めに歯科医院を受診しましょう。
洗口液の長期使用
ほかにも、色素の濃い洗口液を長期間使用すると、全体的に、そして均一に歯に着色します。なかでも、イソジンなどのヨード系洗口液は着色しやすい傾向があり、使用頻度や期間に比例して着色が進行します。
こうした場合、無色透明の洗口液を選ぶか、使用後に水でしっかりうがいすることで着色を軽減できます。歯の表面に限定された着色であれば、専門的なクリーニングでも除去可能です。
ただし、医師の指示で使用する場合は、着色よりも治療効果を優先すべきです。洗口液は口内環境を清潔に保つ効果がありますが、長期使用で着色のリスクもあることも知っておきましょう。
【内因性】歯の変色が起こる6つの原因

次は、内因性の歯の変色を引き起こす主な原因も紹介します。内因性の歯の変色は、歯の内部や、体の内部からの要因で発生するタイプで、主な原因としては以下が挙げられます。
- 加齢による自然な黄ばみ
- エナメル質形成不全による変色
- 神経を抜いた歯の変色
- 歯の神経の損傷や死滅
- テトラサイクリン系抗生物質の影響
- 薬の副作用による変色
加齢による自然な黄ばみ
年齢を重ねると、自然と歯が全体的に均一に黄色みを帯びてくる変色が起こります。歯の表面のエナメル質が徐々に薄くなり、内部の象牙質の黄色が透けて見えるためです。象牙質はもともと黄色で、年齢とともに分厚く濃い色になる傾向があるのも要因です。
通常、エナメル質は半透明で、噛み合わせや歯磨きでも徐々にすり減っていきます。また、痛みなどの症状はなく、20代後半からはじまるケースもあります。
こうした加齢による変色は自然な現象ですので、健康上の問題はありません。ただし、見た目が気になる場合は、ホワイトニングなどの治療で改善できます。
エナメル質形成不全による変色
エナメル質形成不全症は、歯の外層であるエナメル質がきちんと作られないことで起こる状態です。
エナメル質が薄いため、象牙質の黄色が透けて見えやすくなり、歯の色が濃い白色や黄色、茶褐色などに変色して見えます。また、歯の表面に白い斑点や線が見られたり、部分的に凹凸があったりする場合もあります。
原因は遺伝的要因や栄養不足、高熱などの全身疾患、外傷などさまざまです。遺伝的な場合は全体的に、後天的な場合は一本単位で症状が現れる可能性もあります。
場合によっては、見た目の問題だけでなく、虫歯になりやすいなどの機能的な問題も伴うことがあります。症状の程度や範囲によって、最適な治療法が異なりますので、歯科医師と相談しながら治療計画を立てましょう。
神経を抜いた歯の変色
神経を抜いた歯(無髄歯・失活歯)は時間の経過とともに、特定の1本だけが暗い色に変色するケースも内因性の代表例です。
通常、歯の根管内には血液が流れ、酸素や栄養を歯に送り届けています。神経を除去すると、この血管も取り除かれ、血液の循環ができなくなります。
その後、時間の経過とともに歯の内部から変色がはじまり、エナメル質を透過して外から見えてしまうのです。神経の治療によって血液の成分などが細管内に入り込むケースでも同様の変色を引き起こします。
歯の神経の損傷や死滅
先に触れたように歯の神経への損傷は、特定の1本だけで変色を引き起こす原因です。これには病変等、例えば神経を抜く治療(根管治療)をした歯や、外傷で神経が死んだ歯でも発生します。この場合、徐々に灰色や黒っぽい色に変わり、痛みはないことが特徴です。
また損傷や死滅の場合は、死んでしまった歯髄の残骸や血液中の鉄分が象牙細管に入り込み、変性して黒くなるケースも含みます。外傷であれば、数年後に突然変色を引き起こすといったこともあります。あとからでも変色に気づいたら、早めに歯科医師に相談しましょう。
テトラサイクリン系抗生物質の影響
テトラサイクリン系抗生物質の影響を受けて、「テトラサイクリン歯」と呼ばれる歯の変色を引き起こすことがあります。主に、歯の形成期(0〜12歳ごろ)に、この抗生物質を大量に摂取すると発生します。
テトラサイクリン歯とは、テトラサイクリン系抗生物質により変色した歯のことで、主な変化は以下のとおりです。
| 評価項目 | 第一度 | 第二度 | 第三度 | 第四度 |
|---|---|---|---|---|
| 変色の特徴 | 歯全体が一様に変色 | 歯全体が一様に変色 | 濃い灰色や青味がかった灰色への変色 | 全体的に着色が強い |
| 縞模様 | なし | なし | 明確な縞模様あり | 明確で濃い縞模様あり |
| 色合い | 淡い黄色、褐色、灰色 | 第一度より濃い色 | 濃い灰色や青みがかった灰色 | 濃い色合い |
| 推奨される治療法 | デュアルホワイトニング | デュアルホワイトニング | 1年程度のデュアルホワイトニング、状況によりラミネートベニア | ラミネートベニアやセラミッククラウン |
| 治療の見通し | 半年程度のホワイトニングで「白くなった」と感じるほど改善可能 | 第一度より時間がかかるが、半年程度で効果を実感可能 | 縞模様は残るが全体的に明るくなり「目立たなくなった」と感じる程度の改善が可能 | ホワイトニングだけでは満足のいく改善が難しく、歯を覆う治療が効果的 |
テトラサイクリン系抗生物質は、かつて風邪薬のシロップに使われていました。これに含まれる黄色味を帯びたテトラサイクリンが象牙質のカルシウムと結合し、象牙質に沈着することで変色が起こります。変色の程度によって最適な治療法が異なりますので、専門医の診断を受けることが重要です。
薬の副作用による変色
最後に、特定の薬剤の服用によって歯に変色を引き起こすこともあります。もっとも有名なのは先に触れたテトラサイクリン系抗生物質による変色ですが、それ以外にも、以下のような薬剤が原因として挙げられます。
- 過剰なフッ素:白い斑点状の変色(斑状歯)
- 鉄剤:黒っぽい変色
- 洗口液(イソジンなど):長期使用で茶色い着色
薬の副作用による歯の変色は、特定の薬剤の服用歴がある人に見られる特徴的な変色です。洗口液であれば外因性となりますので歯の外側だけの清掃で対処できますが、それ以外は内因性がほとんどです。
薬剤による変色の治療法は、変色の種類や程度によって異なります。なかでも子どもの場合は、歯の形成期に影響を与える薬剤には注意しましょう。
歯の変色で気づける病気のサイン

ここまでお伝えした歯の変色は、単なる美容上の問題ではなく、健康上の問題を示すサインとしても有用です。特定の変色パターンは、早急な対応が必要な状況を示す可能性があるからです。
| 症状 | サイン |
|---|---|
| 急に現れた黒や茶色の斑点、初期の虫歯では歯の一部が白く濁る | 虫歯 |
| 歯の表面が粗くなりながらの変色 | 重度の虫歯 |
| 歯ぐきとの境目の黒ずみ | 歯石の蓄積・歯周病 |
| 一本だけが灰色や黒色に変化 | 歯の神経の異常 |
変色に加えて痛みや腫れがある場合は、特に注意が必要です。いずれも、早期発見・早期治療が重要なため、気になる変色があれば歯科医院での診断を受けましょう。
歯科医院での診断が必要な変色
歯の変色のなかには、自己判断せずに専門家の診断を受けるべきものもあります。特定の症状は、より深刻な問題を示している可能性もあるからです。
専門家の診断が必要な変色症状としては、以下のとおりです。
| 症状 | サイン |
|---|---|
| 痛みを伴う歯の変色 | 虫歯・歯髄炎(神経の炎症) |
| 急激に進行する変色 | 活動性の高い虫歯・内部の問題 |
| 外傷後に現れる変色 | 神経へのダメージ |
| 子どもの歯に見られる異常な変色 | 発育上の問題・全身疾患 |
この症状は、単なる美容上の問題ではなく、健康上の問題を示していることが考えられます。病気のサインと合わせて、早期診断・早期治療がより良い結果につながります。
西蒲田デンタルクリニックでは、歯の変色に対してセラミックでの治療を行えるほか、必要に応じてクリーニングも可能です。少しでもお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
>>西蒲田デンタルクリニックのセラミック治療についてはこちらから
歯の変色を予防する5つの方法

歯の変色は完全な予防が難しいですが、適切なケアで進行を遅らせることは可能です。主な歯の変色を予防する方法は、以下の5つです。
- 正しいブラッシングの習慣を確立する
- 歯間ブラシ・フロスを活用する
- 色素の強い飲食物の摂取を制限する
- 禁煙または喫煙量を減らす
- 定期的に歯科検診を受ける
正しいブラッシングの習慣を確立する
歯垢を放置すると変色や黄ばみが進行するため、正しい歯磨きが重要です。食後は早めに歯を磨き、歯垢がたまる前に歯を清潔に保つことができます。正しいブラッシングのポイントは、以下のとおりです。
- 食後30分以内に歯磨きをする
- 1回の歯磨きは3分以上かける
- 歯と歯茎の境目を丁寧に磨く
- 力を入れすぎず、小刻みに動かす
食後だけでなく、間食や喫煙のあとにも歯磨きをすることが理想的です。歯ブラシは3か月を目安に交換し、毛先が開いたものは使わないようにしましょう。
正しいブラッシング技術を身につけるだけでも、歯垢の蓄積を防ぎ、歯の変色を予防できます。うまくいかない場合は、歯科医院で正しいブラッシング方法を指導してもらうことも有効です。
歯間ブラシ・フロスを活用する
とはいえ、歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを完全に除去できないケースも少なくありません。歯間ブラシやフロスを使うことで、歯ブラシが届かない部分の歯垢も除去できます。
歯間部分は歯垢がたまりやすく、変色や虫歯のリスクが高い場所です。歯間ブラシは、歯と歯の間のスペースが広い場合に効果的ですので、歯の形状に合った適切なサイズを選びましょう。
また、毎日1回は歯間ブラシやフロスを使用するだけでも効果があります。無理な力をかけず、優しく使用することがポイントです。ただし、どちらも実際に使ってみたときに出血が見られた場合は、歯肉炎や歯周病を疑います。可能であれば、歯科医に相談しましょう。
色素の強い飲食物の摂取を制限する
色素の濃い飲食物は、歯の着色の主な原因です。以下のような飲食物の摂取を控えるか、摂取後のケアを徹底することが大切です。
- コーヒー
- 紅茶
- 赤ワイン
- カレー
- チョコレート
- 烏龍茶
完全に避けるのは難しいため、摂取後に水でうがいをする習慣をつけるのが有効です。ストローを使って飲むだけでも、前歯への着色を軽減できる飲み物もあります。
また、色の濃い飲食物の摂取後は、可能であれば30分以内に歯を磨きましょう。ただし、酸性の飲食物を摂取した直後は、エナメル質が弱くなっているため、30分ほど時間を置いてからの歯磨きをおすすめします。
禁煙または喫煙量を減らす
タバコのヤニは歯の変色を引き起こしてしまうため、禁煙または喫煙量の削減で新たな着色を防ぐことができます。禁煙であれば、新たな着色を防げるだけでなく、口臭や歯周病のリスクも低減できます。
どうしても禁煙が難しい場合は、喫煙後すぐに水でうがいをする習慣をつけるだけでも効果があります。ただし、禁煙は歯の健康だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えるものです。
禁煙を考えている方は、歯の美しさを保つためにも、ぜひチャレンジしてください。なお、歯の色が気になる場合、3か月に1回程度の定期的なクリーニングでタバコによる着色を除去できます。
定期的に歯科検診を受ける
最後に、定期的な歯科検診で早期の変色や問題の早期発見も非常に重要です。3〜6か月に1回の受診が理想的で、初期虫歯の早期発見が可能なほか、ブラッシング指導も受けられることで日常のケアの質も向上できます。
また、プロによるクリーニングでは、自分では落とせない歯垢や歯石、汚れも除去可能です。定期的なクリーニングで歯の自然な白さを維持しやすくなりますし、変色の原因を特定して適切なアドバイスや治療法の提案も受けられます。
当院では、患者様1人ひとりの歯の状態に合わせた丁寧なクリーニングと、変色予防のためのアドバイスを提供しています。セラミックでの治療も検討できますので、歯の変色でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
>>西蒲田デンタルクリニックのセラミック治療についてはこちらから
歯の変色を改善する6つの治療法

ここからは、歯科医院で受けられる歯の変色を改善する以下の治療法を紹介します。
- 歯のクリーニング
- ホワイトニング
- ラミネートベニア
- セラミッククラウン
- インターナルブリーチ
- ダイレクトボンディング
歯のクリーニング
歯科医院でのプロのクリーニングは、表面的な着色汚れを除去する方法です。専用の機械や器具を使って、自分では落とせない汚れも除去できます。主な手法としては、以下が挙げられます。
- 超音波スケーラー
- エアフロー
- 歯面清掃(PMTC)
保険適用の場合もあり、なかでもコーヒーやタバコなどによる外因性の着色に有効です。また、定期的に受けることで、歯の自然な白さも維持できます。
加えて、虫歯や歯周病の予防にもつながるため、歯の健康を総合的に守ることができます。クリーニング後は歯の表面がツルツルになり、新たな汚れがつきにくくなるというメリットもあります。
歯科クリーニングは痛みもほとんどなく、短時間で終わる治療です。歯の変色が気になる方は、まずはクリーニングからはじめてみることをおすすめします。
ホワイトニング
ホワイトニングは、専用の薬剤を使って歯を漂白する治療法です。歯の表面に沈着した色素を分解し、光の屈折も変えることで白く見せます。
以下の3種類があり、歯を削らずに白くできる方法としてクリーニングと同様に選びやすい選択肢です。
- オフィスホワイトニング:歯科医院で行う即効性のある方法
- ホームホワイトニング:自宅でマウスピースを使って行う方法
- デュアルホワイトニング:上記2つを組み合わせた方法
この場合、加齢による黄ばみや軽度のテトラサイクリン歯に有効です。ただし、効果は永久的ではなく、定期的なメンテナンスが必要です。また、虫歯や進行した歯周病がある場合は、治療してからホワイトニングを行います。
ラミネートベニア
ラミネートベニアは、歯の表面を薄く削り、セラミックやジルコニア製の薄いシェルを歯の表面に接着性レジンで貼り付ける治療法です。変色だけでなく、歯の形や隙間も同時に改善できるという特徴があります。
歯を最小限に削る(0.3〜0.5mm程度)だけで、自然な見た目と透明感を再現できます。耐久性があり、変色しにくいのも特徴です。
ラミネートベニアは基本的に自由診療(保険適用外)ではあるものの、重度のテトラサイクリン歯やエナメル質形成不全など、ホワイトニングでは改善しにくい変色に効果的です。
セラミッククラウン
セラミッククラウンは、歯をラミネートベニアよりも削り、セラミック製の被せ物をする治療法です。主な種類には、内側を金属で補強したメタルボンドと、内側もセラミックのオールセラミックがあります。
セラミッククラウンであれば、変色した歯を完全に覆い、新しい見た目を作り出すことが可能です。強度が高く耐久性にも優れ、自然な見た目と透明感を再現できるという特徴もあります。
自由診療(保険適用外)が一般的ですが、主に神経を抜いた歯や大きく欠けた歯、重度の変色に適しています。すでに大きく損傷した歯や神経を抜いた歯の場合は、強度と審美性を両立できるセラミッククラウンが最適な選択肢となるでしょう。
>>西蒲田デンタルクリニックのセラミック治療についてはこちらから
インターナルブリーチ
インターナルブリーチは、神経を抜いた歯の内側から漂白する治療法です。歯の外側からのホワイトニングとは異なり、歯の内部にホワイトニング剤を注入してアプローチします。
「ウォーキングブリーチ」とも呼ばれ、歯を削らずに元の形を保ちながら白くできるという特徴があります。通常、週に1回程度の通院を2〜3回繰り返すことが一般的で、効果はすぐには現れず、数日間かけて徐々に白くなっていきます。
基本は自由診療(保険適用外)、また神経を抜いた歯にのみ適用可能です。なお、破折リスク(歯の根が割れる危険性)があるため、慎重な判断が必要です。治療を検討する際は、歯科医師と十分に相談することをおすすめします。
ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディングは、歯の表面をレジン(歯科用プラスチック)で覆う治療法です。歯を最小限に削り、コンポジットレジンという樹脂を埋め、周りの歯に合わせた色や形状を整えます。
変色部分を最小限に削り、その場で修復できるという特徴があります。必要に応じて修正や再治療が可能ではあるものの、こちらも自由診療(保険適用外)となるのが基本です。
ダイレクトボンディングは、特にホワイトスポット(白い斑点)や部分的な変色に有効です。ただし、広範囲の変色や重度の変色には、より耐久性の高いほかの治療法が適していることもあります。
変色した歯の治療にかかる費用の目安

歯の変色の治療費用は、治療法や歯科医院によって異なります。以下に一般的な費用の目安を紹介します。
| 治療法 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 保険適用のクリーニング | ||
| スケーリング(歯石除去) | 約1,000~3,000円 | 保険適用 |
| 歯面清掃 | 約2,000~3,000円 | 保険適用 |
| 定期検診と合わせて | 約3,000~5,000円 | 保険適用 |
| ホワイトニング | 自由診療 | |
| オフィスホワイトニング | 約15,000~30,000円/回 | 即効性あり、複数回必要 |
| ホームホワイトニング | 約30,000~50,000円 | マウスピース代含む初回費用 |
| デュアルホワイトニング | 約50,000~120,000円 | もっとも効果的だが高額 |
| メンテナンス用ジェル | 約3,000~5,000円 | |
| ラミネートベニア | 自由診療 | |
| 1本あたり | 約80,000~120,000円 | 材質により価格変動 |
| 前歯6本の場合 | 約480,000~720,000円 | 10年以上持続することも |
| セラミッククラウン | ||
| メタルボンド | 約80,000~100,000円/本 | 自由診療 |
| オールセラミック | 約100,000~150,000円/本 | 自由診療 |
| ジルコニア | 約120,000~180,000円/本 | 自由診療 |
| CAD/CAM冠 | 約5,000~7,000円/本 | 保険適用(前歯・小臼歯限定) |
| インターナルブリーチ | 約5,000~20,000円/本 | 自由診療、2~3回の通院 |
美容目的の治療は自由診療になるため、治療前に費用の説明を受け、納得したうえで治療をはじめることが大切です。保険適用の治療と自由診療の違いや、それぞれのメリット・デメリットについても聞いておきましょう。
まとめ
歯の変色は外因性と内因性の2つに大きくわけられ、それぞれ原因や対処法が異なります。
外因性の変色は主に食べ物や飲み物、タバコなどによる表面的な着色で、歯科クリーニングやホワイトニングでの改善を狙えます。一方、内因性の変色は歯の内部、体の内部からの影響によるもので、より専門的な治療が必要です。
歯の変色は見た目の問題だけでなく、健康上の問題を示すサインになることもあります。変色に気づいたら、自己判断せずに歯科医院で適切な診断を受けることが大切です。
当院では、患者様1人ひとりの歯の状態に合わせた最適な治療プランをご提案しています。歯の変色でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。セラミック治療を含め、美しく健康な歯を取り戻すお手伝いをいたします。
>>西蒲田デンタルクリニックのセラミック治療についてはこちらから
よくある質問(FAQ)
歯が急に変色するのはなぜですか?
歯が急に変色する主な原因は、以下のとおりです。
- 外傷による内出血(歯を強く打った場合)
- 急性の虫歯の進行
- 神経の急激な壊死(死滅)
- 歯の内部での細菌感染
歯が急に変色する場合は、外傷や虫歯、神経の問題など健康上の問題が考えられるため、早急に歯科医師の診断を受けることが重要です。なかでも痛みを伴う場合や、外傷後に変色が現れた場合は、早めの受診をおすすめします。
歯が茶色くなったのはどうしたら治りますか?
歯が茶色くなる原因には以下があり、原因によって対処法が異なります。
- 外因性の着色(コーヒー、タバコなど)→ 歯科クリーニングやホワイトニング
- 虫歯による変色 → 適切な虫歯治療
- テトラサイクリン歯 → ホワイトニングまたはラミネートベニア
- 古い詰め物の変色 → 詰め物の交換
歯が茶色くなった場合は、まず歯科医院で原因を診断してもらい、その原因に応じた適切な治療法(クリーニング、ホワイトニング、修復治療など)を選ぶことが大切です。自己判断での対処は避け、専門家のアドバイスを受けましょう。
歯の変色はもとに戻りますか?
歯の変色がもとに戻るかは、変色の原因と程度によって異なります。
- 外因性の着色(飲食物、タバコ) → クリーニングで除去可能
- 加齢による黄ばみ → ホワイトニングで改善可能だが、時間とともに再び黄ばむ
- テトラサイクリン歯 → 完全には戻らないが、ホワイトニングやラミネートベニアで見た目を改善できる
- 神経を失った歯 → インターナルブリーチやクラウンで見た目を改善できるが、根本的な原因は解決しない
表面的な着色は比較的簡単に除去できますが、内部からの変色は完全にもとに戻すのが難しいです。完全に「もとに戻る」というよりは、「改善する」と考えるのが現実的です。早期の対応ほど良い結果が期待できますので、受診を検討しましょう。
歯がグレー色になるのはなぜ?
歯がグレー色になる主な原因は、以下が挙げられます。
- 神経が死んだ歯(失活歯)
- 外傷による内出血
- テトラサイクリン系抗生物質の影響
- 金属イオンの歯への浸透
歯がグレー色になるのは主に神経の問題や薬の影響、外傷などの内因性の原因によるものです。なかでも一本だけがグレー色に変色している場合は、神経の問題や外傷が考えられます。このような変色は専門的な治療(インターナルブリーチやクラウン治療など)で改善できるケースも含むため、歯科医師に相談しましょう。